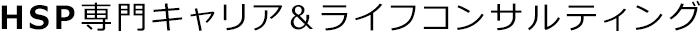HSPか発達障害かで悩んでいる方へ ~HSP以外のことが理由で起きる生きづらさとは~

自分が周りとは「なんとなく違う」と感じたことをきっかけに、いろいろと調べてHSPと出会い、腑におちた!と感じる方が増えてきていますね。
一方で、「この”違和感”って、発達障害なのかなあ・・・でも、病院にいくのは勇気がいるなあ・・・」とスッキリしない方もいらっしゃいます。
もしあなたが、HSPか発達障害なのかで迷っていて、実生活でもなんらかの支障を感じていたら、HSPについてだけでなく、発達障害について調べるのも一つのヒントになると思います。
この記事では、HSP以外のことが理由で起きる悩みや、発達障害を理解するのに役立つ情報をお伝えします。
「敏感すぎる」だけではHSPとは断言できません
ここ数年、日本では、「敏感すぎる」「繊細」といった表現とともにHSPが語られています。私も、「敏感すぎる」というフレーズを使って発信しているもののひとりですが、気を付けていることがあります。
それは、HSPは敏感すぎるだけではない、を明確に伝えること。
HSPか、そうではないかをみわけるには「HSPの4つの特徴」を知る
では、あらためて、HSPはどういうものなのでしょうか。
すでにご存知の方も多いとおもいますが、HSPは4つの特徴があり、この4つ全てに当てはまることがHSPとされています。
HSPの4つの特徴:
- 深い処理
- 神経の高ぶりやすさ
- 感情反応の強さ
- ささいな変化・違いに気がつきやすく、影響を受けやすい
HSPの4つの特徴の一部が当てはまる場合は、私は、「HSPではないが感受性がするどい」などと整理していて、お悩みへの対策は、ほとんどが、HSPの方向けのものと重なります。
私が気を付けているのは、4つの特徴以外の側面でも、生きづらさをかかえている場合です。
HSPと発達障害は混同されることがある
- 音やにおいに敏感すぎて辛い。
- 自己肯定感が低く、人間関係が辛い。
こういった傾向はHSPにも見られますが、HSP以外のことが原因で悩んでいる可能性もあります。
「HSP以外のこと」にはいろいろありますが、たとえば発達障害とHSPが混同されている場合があります。
HSPとADHDの混同 ~ E.アーロン博士の見解 ~
アーロン博士によると、HSPとADHDは混同されやすいとのことです。
「静かな場所での作業を好むのであればHSP」とのことですが、私がお会いしたADHDの方の中には、音に敏感な方もいらっしゃいました。
ことばだけで気質や発達障害のことを伝えるって難しいな、と思います。
HSPもADHDも、こういう行動面がある、と絶対的にあてはめることは難しいんですね。
静けさといっても、基準は人それぞれあって、私が許容できる「静けさ」の範囲と、他の方が許容できる範囲は異なりますよね。
静けさを好むだけでHSPかADHDかを明確に判断することはほぼ不可能です。
この点は、アーロン博士も、「何らかの障害や疾患かなと感じるなら、その方面の専門家に相談してください」ということを、ブログやサイト、書籍で書いていらっしゃいます。
すんなりとHSPと断言できない状況では、各種方面の専門家や他の発信者の方々の見解を頭にいれながら、たとえば音に関すること以外の側面もてらしあわせて、HSPらしさの有無を確認することにしています。
HSPと間違えられやすい職場での問題
HSPなのか、他のことが原因で悩みがあるのか、がすぐわかる場合もあれば、何度かお話を伺ってわかるときもあります。たとえば、「仕事の覚えが遅い」というフレーズでだけでHSPと判断しきれません。
具体的に説明した方が伝わりやすいので、仕事や働き方に関するご相談で取り上げられることのある、HSP以外の可能性がある例を、ご参考までにいくつかご紹介します。
なお、これらは一例にすぎません。ほかの例もありますし、解釈もケースバイケースです。そして、ここに書いた内容だけで病気や症状の診断が下ることは決してありません。
あくまでも、HSPと間違えられやすいケースをイメージしていただくための説明としてお読みください。
仕事の覚えが遅い
HSPは、新しい環境や、初めて取り組むことで成果がでるまでに時間がかかることがあります。
仕事の全貌、自分の作業の位置づけ、自分の作業が及ぼす影響、仕事の目的など、全体像も詳細もすべて腑におちるまではなかなか作業がはかどらない傾向があります。
その一方で、半年から1年ほどたつと、仕事もできるようになり、優れた結果を出すことも多々あります。
どんなに説明されても、何年たっても作業ミスがある・指示が理解できないなど成果が見えてこない場合は、HSP以外の何かが原因である可能性があります。
マイペースで作業をしたい
マイペース、とは「自分なりのやり方と進める度合い」のこと。
HSPは、作業の進み具合を逐一チェックされる状態がとても苦手です。
チェックされている状況や、チェックを入れてくる人の思考や感情に引きずられてしまうのです。
加えて、予定よりも時間がかからないように、ミスがないように・・・と慎重になりすぎて、結局時間がかかったりすることがあります。
マイペースや時間の管理について、「気がついたら予定の時間を大幅に過ぎていた」「時間の決まりがあることが耐えがたい」という感覚が強い場合は、HSPとは違う原因の可能性があります。
こだわりが強いと言われる
HSPは、慎重にことを運んだり、総合的な判断のもとに結論を出す、という感覚ゆえに、「こだわりがあるねえ~」と言われる場合があります。
ですが、時に、変更が起きることもあり得ると心得えています。
変更そのものが全く理解できなくて、パニック状態におちいるほど激しい場合は、HSP以外の可能性があります。
会話には問題がないが、漢字や算数が苦手
誰にでも得意・不得意はありますが、HSPの場合は、「やらなければならないことだ」と判断すると、ムリしてやり遂げようとします。
その結果、ある程度(またはとても)できるようになることが多いです。
どんなに努力を重ねても、漢字が覚えられない・計算ができない・数え間違えてしまうといった場合は、HSP以外のことが原因である可能性があります。
片付けが苦手
忙しくて時間に追われる現代人にとって、家事や片付けに時間がまわせない・・・とストレスに感じることは多いですよね。
時間がとれれば片付けができるのであれば、何とかして時間をやりくりすることが解決になります。
もし、時間があったとしても、片付ける気があったとしても、いつのまにか他のことをしてしまって片付かない場合は、HSP以外のことが関係している可能性があります。
周りが自分の陰口をたたく
HSPは、雰囲気を察しやすく、他の人の考えや気持ちをある程度(ですがかなり正確に・・・)感知してしまいます。
感知する内容は、喜怒哀楽すべて。
楽しんでいる人がそばにいると、まるで自分のことのように楽しい気持ちになり、ふさいでいる人がそばにいると、自分の心まで苦しくなってきてしまいます。
そして、自分のせいで周りが不愉快な思いをしているのではないか?と気になってしまうのです。
他人の気持ちや考えに同調しすぎてしまい、自分がわからなくなる、とか、自分の意見を言えずに困る、というのがHSPの悩みです。
もし、「周りがいつも私の陰口をたたく」というように、周囲から攻撃されていることを「周りの気持ちがわかりすぎる」と感じている場合は、HSP以外のことが原因である可能性があります。
指示や会話が理解できない
友達との会話で大きな問題はないのに(時々アレ?っという顔はされるが、大勢に影響はない)、仕事のハナシは何か月、何年たっても理解が追い付かない場合は、HSP以外のことが原因である可能性があります。
HSP・疾患・発達障害への対処
HSPなのか、それ以外なのかを重要視する理由は、対処を間違えると事態が悪化する可能性があるからです。
個人的な経験なのですが、私の元夫は発達障害がありました。
当時、発達障害に少し詳しい方に、安易な気持ちで相談をしたのですが、その方は専門家ではなく、対処を誤りました。
その結果、元夫も私も、一生心に傷を抱える結果となったのです。
私は、専門性が必要な悩みには、専門家へご相談いただきたいと強く思っています。間違った対応は、自尊心を深く傷つけ、社会生活にも大きな影響を及ぼすからです。
HSPは疾患でも障害とも別ですが、HSPにははっきりとした特徴があり、特徴を理解している専門家によるサポートが最も有効です。
何らかの疾患がある場合は、治療が最優先です。治療の方針は、医師と相談する必要があります。
発達障害が関係する場合は、メンタル面だけケアしても、根本的な改善が見られるとは限らないと言われています。
発達障害からくる鬱や適応障害など(二次障害といいます)を改善するには、発達障害への自己理解を深めつつ、社会生活をおくるうえでのサポートが必要だからです。
また、働き方・仕事や職場の選び方や、受けられる支援も、HSPかそれ以外かで変わってきます。HSPには公的支援はありませんが、疾患・発達支援にはあります。
発達障害や疾患の情報を得ても、まだHSPかどうかスッキリしない方は、一度時間をとって、HSPについてじっくりと学ぶことをおススメしています。